試験では正解でも、現場では通じない?──数字に“意味”を持たせるMQ会計の面白さ
投稿日:2025年06月24日
導入
税理士を目指している方や、すでに実務に携わっている方なら、「これは経費になりますか?」という質問に何度も向き合ってきたことでしょう。
税法に基づいて、これはOK、これはNGと判断を下すのが私たちの役目──確かに、それは試験勉強の成果が活きる瞬間です。
でも、現場に出て経営者と向き合うと、それだけじゃ済まない場面に直面します。例えば、ある経営者が仕事を紹介してくれた相手に100万円の商品券を渡した場合、それは税務上「交際費」扱いになって、制限の対象になるかもしれません。でも、その100万円が何千万円という売上や利益に繋がったとしたら?
今回は、そんな「数字の裏側にある意味」に注目し、MQ会計という考え方から経営と会計の面白さを見ていきましょう。
税法の正解と経営の現実のギャップ
「これは経費になりますか?」という質問の落とし穴
税理士の仕事は、法律に基づいて正確な処理をすること。だから、「契約書がないから紹介料は交際費になる」「交際費が一定額を超えると損金不算入になる」といった判断は、まさに税理士としての”正解”です。
でも、それをそのまま「だからダメです!」と伝えるだけで、経営者の心には届くでしょうか?
経営判断としての「アリかナシか」
例えば、経営者が紹介してくれた相手に高額な商品券を渡すことで、新たな売上ルートが開ける可能性がある。つまり、目の前の費用を単なる「無駄遣い」と断じるのではなく、それが将来的にどう利益に繋がるかを考える視点が求められます。
税法上は問題があっても、経営の現場では「意味があるかどうか」で判断される場面もあるのです。
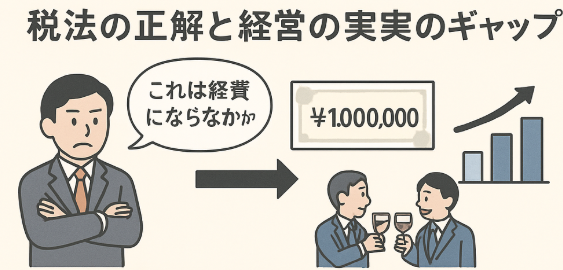
MQ会計が教えてくれる「数字に意味を持たせる」感覚
MQ会計って何?
MQ会計では、「売上高(PQ)=販売数量(Quantity)×単価(Price)」というシンプルな式をベースに、経営の意思決定とその成果を数字で読み解く手法です。です。
この会計の魅力は、単に「数字を作る」ことではなく、「数字の背後にある経営判断や行動の意味」を読み解くことにあります。
行動が数字にどう現れるか
たとえば、ある飲み会の費用が高額だったとしても、それがきっかけで信頼関係が築かれ、そこから大きな仕事に繋がる、仕事量が増える──そんなことも現場では起こります。
その飲み代は、単なる交際費ではなく、将来の売上や粗利に変わる“投資”だったかもしれません。
数字の結果で行動を評価する
会計の数字は、経営の結果を表す「報告書」です。だからこそ、行動の是非を判断するには、結果として売上や利益にどう繋がったかを見る必要があります。
そして、それがMQ会計の真骨頂。「売上や粗利がどう変化したか」を通して、経営判断の成果を見極めるのです。
試験の知識を超える現場の知恵
試験勉強では「正解」がある
税理士試験では、「これは経費になる」「ならない」という明確なルールが問われます。その意味では、試験の世界は”白黒”がはっきりしています。
現場では「意味」が問われる
でも、実務ではグレーゾーンも多く、「その行動に意味があったのか」「会社全体としてプラスになるのか」が問われます。
「税法上ダメだから使わない」ではなく、「たとえ税務上マイナスでも、それ以上のメリットがあるかもしれない」と考える柔軟性が、現場での価値を生むのです。
まとめ:数字に“意味”を持たせることが経営の鍵
税理士や会計担当者にとって、正確な処理は基本です。でも、それだけでは経営者の心には届きません。数字の背後にある「行動の意味」や「判断の背景」を読み取り、それを経営者と共有することができれば、会計の仕事はもっと面白く、価値あるものになります。
MQ会計は、そのための強力なツール。数字を「結果」ではなく「意味」として読む力が、これからの税務・会計実務には求められているのです。
▼経営に役立つ情報をもっと知りたい方は
→ メルマガ登録はこちら
→ 丸山会計へのお問い合わせはこちら
この記事の監修

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。



