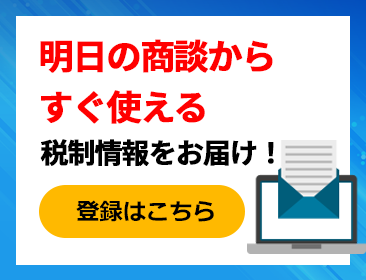役員見舞金の限度額、いくらまでなら福利厚生費で大丈夫なのか
投稿日:2022年09月07日
会社の役員や従業員がケガや病気で入院したとき、会社の経費として見舞金を渡すケースがあると思います。ポイントを抑えてさえいれば問題はないのですが、雑に扱っていると調査で否認されることもあります。
この記事では、役員や従業員へ渡す見舞金は、いくらまでなら福利厚生費で処理できるのか、また調査で否認されないためのポイントについて解説します。
1.見舞金の位置づけと限度額について
見舞金は一般的に慶弔見舞金と言われるものの一つです。役員や従業員がケガや病気をしたときに支払うのですが、これは義務ではなくそれぞれの会社が独自の規定を作成する福利厚生制度の一つとなります。
しかし独自に決められたとしても、全額が福利厚生費として認められるわけではありません。
まずは見舞金が会社にとってどのようなものなのか考え、いくらまでが妥当な金額なのかを考えてみましょう。
見舞金と税法上の取扱い
見舞金とは、一般的には親しい人がケガや病気で入院したとき、お見舞いをする際にお渡しする現金のことです。
個人間であればそれが特に問題になることは少ないですが、会社の慶弔見舞金規定に基づいて、役員や従業員に見舞金をわたす場合はそれが法人の損金となっているため注意が必要です。
それというのも国税庁は法人税法基本通達9-2-9で、法人がした行為で実質的にその役員等に対して給料などを支払ったものと、同様の効果をもたらすものは、経済的な利益として、給料等に含まれるとしています。
しかし、同時に法人税法基本通達9-2-10では、法人税法基本通達9-2-9で経済的な利益の供与をした場合でも、所得税法におてい非課税と認めたれるもので、かつ、その法人が給与として扱っていないものは課税しないとあります。
見舞金とよく間違われやすいのが、所得税法基本通達28-5で、会社の慶弔見舞金規定にありそうな、雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等で、「使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする」とされています。つまり原則は給与所得として源泉所得税が課税されるのです。
しかし、これに続いて「ただし書きで、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、所得税を課税しなくて差し支えない」(所得税法基本通達28-5後段)と書かれているので、不自然な金額でなければ給与所得として課税しないとしています。
そのため結婚出産に伴う祝い金で社会通念上相当を認められるものは、福利厚生費として処理して問題ないことが分かります。
また、見舞金等については、所得税法基本通達9-23で、「葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする」と定められており、見舞金などについては、見舞金などを渡すものとの関係等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、所得税法の非課税と規定されております。
これにより見舞金で社会通念上相当と認められるものについては、所得税を課税しない所得として非課税になります。
社会通念上相当な金額とはいくらなのか?
ここで疑問になるのは「社会通念上相当」という金額がどれくらいかということです。よく見舞金の限度額を調べると「5万円以下であれば問題ない」というアドバイスを見かけます。
実はこの5万円という金額には根拠とされる事例があるのですが、結論からいうと5万円以下であれば必ず認められるわけでも、5万円を超えたから必ず否認されるわけでもありません。
これについて気を付けるべき点は後で解説しますが、少なくとも5万円は絶対ではないことは知っておきましょう。
5万円という金額がはじめて出された事例
見舞金の限度額で頻繁に目にする5万円という金額ですが、これは平成14年6月13日の国税不服審判所で出された判決に基ものがあります。
これは建築工事業を営む同族会社(以後A社とします)が、その取締役会長(以後Hとします)に支払った報酬の額及び退職給与の額が過大か否か並びに同人に支払われた見舞金が経済的な利益として同人に対する賞与等に該当するか否かを主な争点としたものでした。ここでは見舞金についてのみ触れます。
A社はHががんで入院したことで受け取った生命保険の半額を、見舞金という名目で3回にわたり合計3,995,000円をHに支払っていました。判決では入院1回あたり50,000円が「社会通念上相当であると認められる見舞金の額」とし、入院が9回なので50,000円×9にあたる450,000円は福利厚生費として認めるが、これを上回る3,545,000円は役員賞与としました。このポイントは以下の3点です。
①福利厚生費としての見舞金が損金の額に算入されるか否かは、当該見舞金の額が社会通念上相当であるか否かにより判断される
②会社規定に従って支払われたものかどうか及び保険金の原資のいかん並びに会社規定の作成過程及び保険契約の締結過程のいかんによって左右されるものではない
③類似法人のうち見舞金等の福利厚生費の規定が存する8社についてその役員に対する見舞金等の支給状況を検討したところ、その規定している額及び支払例において見舞金の額が50,000円を超えていないことから、入院一回当たり50,000円が社会通念上相当である金額の上限と認められる
まずは福利厚生費としての見舞金は、あくまで励まし慰めるための支出であって、前述した所得税法において経済的な利益として課税しないものに該当し、かつ、会社として給料として扱わなかったものは、給料として取り扱わないものとする。としています。(法人税法基本通達9-2-10)
最終的には「同じ地域で類似法人を調べ、社会通念上認めたれる金額は50,000円であるという結論を出しました。」同一規模の法人を調べた結果、社会通念上認められる金額が50,000円であったため、そのため社会通念上相当であると認められる見舞金の額を5万円としています。
絶対ではないが影響の大きい判決
先ほどの国税不服審判所の判決も、あくまでA社にたいする個別事案なので、見舞金が5万円を超えると絶対給与認定されると決まったわけではありません。
影響が大きい判断であることは確かです。この審判では課税庁側が税務署管内の法人の役員に対する見舞金等の支給状況を検討し、妥当な金額とした3万円も国税不服審判所で認められませんでした。
しかし改めて同業類似法人を8社抽出して5万円としたことから、地域や業界の相場を大きく超える見舞金の福利厚生費計上は慎重にならざるをえません。
改めて言及された見舞金5万円
コロナウイルス感染症に関連した国税庁のQ&Aに、見舞金の金額について言及されています。
その内容は一般的な見舞金と少し趣が違いますが、慶弔基準を改定し「新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言下において介護サービスを実施する従業員については、5万円の見舞金を支給する。」こととした場合、当該金額は非課税所得でよいかという質問です。
これに対し国税庁は、「ご質問の見舞金は、非課税所得に該当しますので、給与等として源泉徴収する必要はありません。」と回答していることから、5万円であれば福利厚生費等として処理できるという一定に基準にはなります。
2.見舞金の支給を給与認定されないためのポイント
国税不服審判所の判決である法人に対して見舞金の上限が5万円とされましたが、法令や通達で明確な金額基準は示されていません。金額については検討の余地はあるものの、少なくとも税務調査で見舞金を給与認定されない準備はしておくべきです。
ここからは最低限必要な準備について説明します。
無くては話にならない慶弔見舞金規定
見舞金を支出するにあたって、基準となる「慶弔見舞金規定」等がなければ、税務調査で支出の根拠を聞かれても答えることができませんし、最低限のものは決めておかなければなりません。
ここで重要なのは、
①国税庁の法人税法及び所得税の基本通達にも出てくる「その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるもの」に合致すること
②役員だけではなく全従業員が対象である必要があります。
③そして、あくまでも労働の対価とは別であるという、性格の支給でなければなりません。
上記のご紹介した国税不服審判所の案件は、生命保険と連動した見舞金の支払が否認されておりますが、その金額が不相当に高額であるという理由で、否認されているものであり、適正額であれば否認はされなかったでしょうか。
そのため社会通念上相当であるというところが大事になってきます。
金額などについては税理士に相談を
慶弔見舞金規定を取り決めるときや、金額については判断が非常に難しいのが現実です。とくに役員に対する見舞金は、税務調査でも目立つ部分なうえ、否認されると役員賞与として損金不算入となるのでダメージが大きくなります。
規定作りやその運用に関しては、税理士などの専門家に相談したりすることをおすすめします。
3.まとめ
本来の見舞金は、福利厚生制度の一部で社員に早く立ち直って欲しいという会社の思いと、社員の思いの痛みを少しでもやわらげるするあるために欠かせないものです。ただ会社によっては経営者のお手盛り支給がみられるのも事実で、同族会社の税務調査では必ずチェックされる項目でもあります。
最近は情報が溢れすぎて、見舞金と福利厚生費についても誤解を招くような解説が散見されます。当記事が見舞金に関する正しい理解にお役に立てたら幸いです。
この記事の監修

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。