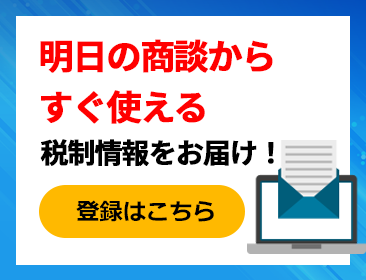国税庁の「事前照会に対する文書回答」の現実と有効性
投稿日:2022年08月10日
税務申告においては、税務上の取り扱いについて悩む事案は多いものです。多くは過去の事例や判例などを参考に判断できるのですが、先例のないものについて何か調べる手立てはないのでしょうか。
このようなときは、国税庁が行っている「事前照会に対する文書回答制度」の利用も選択肢の一つとなります。しかし実際のところ、この制度はどの程度使えるのか分かりづらい部分があります。
この記事では事前照会がどのような制度なのか、そして問題点について解説します。
1.国税局の事前照会とはどのような制度なのか
「事前照会に対する文書回答制度(以下「事前照会」という)」は、平成13年(2001年)9月3日からスタートした制度です。これは同年3月27日に閣議決定された「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」に基づき、各省庁で実施されている制度の国税庁版なのです。
まずは事前照会の概要や流れについて確認していきましょう。
事前照会の趣旨と概要
先ほども触れたとおり事前照会制度が実施された理由は、閣議決定により「民間企業等がある行為を行うに際し、法令に抵触 するかどうかについての予見可能性を高めるため、当該行為について特定の法 令の規定との関係を事前に照会できるようにする」とされたからです。
つまりこれを国税庁の業務範囲に落とし込むと、適切な税務処理の判断がつかないときに国税庁に照会をかけ、その回答を文書でもらうことになります。基本的には納税者サービスの一環であり、照会および回答の内容を公開することによって、他の納税者の予測可能性の向上に役立てるためという目的があるのです。
事前照会制度の利用の流れ
事前照会制度の利用の流れですが、回答を得られるかどうかは別にして次のような流れになります。
まずは税務署に備え付けの(もしくは国税庁ホームページで提供している)「取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会」の用紙に必要事項を記載し、必要な関係書類とともに、所轄税務署の担当部門(法人であれば法人課税部門)に提出します。
提出後に内容の審査と回答を行うのは、国税局の審理課(審理官)又は酒税課(照会が酒税に関するものである場合)で行います。
受付窓口へ提出した日からおおむね1か月以内に、文書回答の可能性や回答時期の見通しについて口頭で回答するとされているのですが、恐らく文書回答まで至らない事例の多くは、この段階でストップするものと考えられます。
弊社が事前に照会した案件でも9割以上は、口頭での回答にとどまります。
国税OB審理担当であった税理士に確認をしてもらったところ、実際には文章回答される案件もあるが、前例が無く今後の模範となる案件でない限り、滅多に文章回答はないとのことでした。
審査の過程では、追加の書類提出を求められることもあり、追加書類のため要した期間を除き、原則3か月以内の極力早期に回答するよう努めるようです(国税庁のホームページによる)。
文書による回答は、「貴見のとおりで差し支えありません。」又は「貴見のとおり取り扱われるとは限りません。」という形式で出されます。後者の回答が必要なのか疑問ですが、決まりなので仕方ありません。
回答の対象となる照会内容
事前照会制度の利用ですが、大前提として「これまでに法令解釈通達などにより、その取扱いが明らかにされていないもの」とあり、当り前ですが調べればわかるものを照会したらただの迷惑行為になります。
回答の対象は、「取引等に係る国税の申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会であること」であって、以下のものは文書回答の対象にはなりません。
①照会の前提とする事実関係について選択肢があるもの
②調査等の手続、徴収手続、酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又は酒類行政に関係するもの
③個々の財産の評価や取引等価額の算定・妥当性の判断に関するもの(例えば、法人税法上の役員の過大報酬等の判定や個々の相続財産の評価に関するものなど)
④提出された資料だけでは事実関係の判断ができず、実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を必要とするもの
⑤その他、この文書回答手続の対象として適切でないと認められるもの
つまり①では「仮定の話には回答しない」ということを言っていて、③では「事前照会を便利使いするな」と言っています。⑤でいう適切でないと認められるものとは、「法令等に抵触する又はその恐れのある取引」や「関係者間で係争中又は係争の恐れのある取引」が該当します。
2.事前照会制度の有効性はあるのか
税務に関する取扱いについて事前に照会する方法は、なにもこの事前照会制度だけではありません。よく利用されるのは事前予約の上、税務署職員と面談での照会・回答があります。
しかし口頭での回答というのは、後に調査で否認されるケースも存在するので、確定的な判断が必要となれば、文書回答手続きをすべきかもしれません。
ここからは「本当に確定的判断」となりうるのか、その有効性を考えてみましょう。
踏み込んだ見解は期待できないが相談記録は残る
事前照会制度を利用する側に立てば、判断のつきかねる税務処理について後で否認されないか確認したい気持ちになるでしょう。正直な心境でいえば「危うい橋なのかの判断」に、国税局のお墨付きを得るようなものです。
しかし国税等の税負担軽減を目的とした(と判断される)取引に対して、国税庁は回答してくれません。また役員の過大報酬や相続税評価額などの回答もしないこととされています。
しかし具体的な金額や査定だけではなく、貸し倒れの判断や組織再編、贈与・相続など、多額の金額が動く取引の判断については、税務処理の考え方について事前照会することが有効であると考えられます。
事前照会の処理は税務当局内で書類が回されながら回答の可否が判断されているので、少なくとも何ら相談しない申告に比べて心証が良いうえ、記録に残っているぶん調査時に余計な疑念を抱かれる可能性が減ります。
国税局としても事前に相談にきている案件について、「あの相談に来ている案件か」となりますので、それなら前に来ていた資料と同じであれば、わざわざその分野での調査を行わなくですみます。
組織再編については特に、適格なのか非適格なのかで、税額が大きく変化することから、事前照会を行い事前照会を行ことは大変有効な手段だと思います。
国税局でも、組織再編については専用の質問場所を設けており、そこに事前照会文章の書き方等詳しく記載されています。
回答においては必ず、 枕詞として組織再編の場合、法人税法132条の2などの適用が無い場合と前提としてという、言葉が入ります。
これはその合併、分割などの行為が、法人税の負担を不当に減少させることを目的としたものでないことということが前提であるということです。
回答までの期間を考えて利用しなければならない
事前照会制度は、提出してから回答を得られたとしても3か月ほど時間を要します。国税庁としても迂闊な回答を出来ないわけで理解は出来るのですが、照会をかける取引の時期によっては少々使いににくいものです。
もし申告期限までに回答がなく、申告後に回答が出された場合、その内容によっては修正申告や更正の請求が必要になることも考えられます。
このことを考えると、税理士と関与先企業の日ごろからのコミュニケーションは重要で、事後的な取引の確認だけではなく、将来的な展望や計画についても確認をし、判断が難しい案件について先回りしておく必要があるでしょう。
非常に少ない受付件数や相談しない理由
事前照会制度は、スタート当初から受付件数の低さが指摘され続けてきました。最初の1年間で55件の受付件数だったものが、最近でもそれほど増えていないようです。
「国税庁レポート2020」によると、平成30年度で133件、令和元年度で115件という受付件数となっています。
これには複数の理由が指摘されていますが、なかには制度自体を知らない税理士や、「税務処理の判断を税務署にお伺いをたてるのは税理士のプライドに係わる」と考える方もいるようです。
しかし税務処理の判断ミスは最終的に納税者の負担になることを考えると、事前照会などを含めてあらゆる対策をしておくことが、納税者ばかりか税理士も守ることになるのです。
3.まとめ
税務に携わっていると、処理について悩む場面が多くあります。ただ事前照会制度を使おうかと考えたとき、躊躇する気持ちも感じる制度です。
しかし正攻法で国税庁に照会するだけの制度で、文書回答を得られないケースでも記録が残ることから、事前照会制度はかなり有効性の高い手続きだといえます。
申告後に不安を感じないためも、積極的に活用すべき制度が事前照会なのです。
この記事の監修

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。